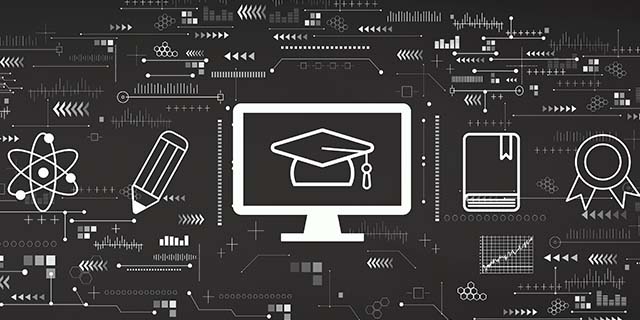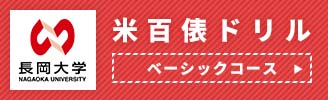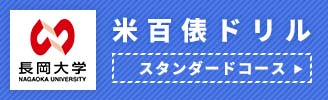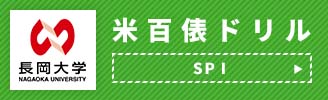学部紹介Faculty
Researchers
教員紹介
専門、主専攻
世界経済論
主な担当科目
国際経済学、世界経済論、大学を飛び出して地域を知ろう、キャリア開発Ⅱ-1、英語ⅠC・英語ⅢD、ゼミナールⅡ前・Ⅱ後・Ⅲ・Ⅳ
研究テーマ
- 地域経済の国際比較からの総合的分析
- 新潟県における商工会と地域発展の研究
- アメリカの国際政治経済戦略の研究
研究業績
著書
| 平成10年9月 | JAPANOLOGY CLASS − The Dynamic Transference of Japan − related Knowledge to The Entire World for The Creation of Splendid Global Society(Single Work)(多賀出版) |
|---|---|
| 平成8年10月 | 『テイクオフの経済政策—産業国家離陸の経済政策〜MITIの戦略産業育成政策』(単著)(多賀出版) |
論文
| 令和7年1月 | Super Powers and Strategic offensive Arms Control Negotiations - Overview of SOA Control Talks,from SALT by Nixon and Brezhnev to New START by Obama and Medvedev - 『研究論叢』第23号 |
|---|---|
| 令和6年1月 | 「フォード政権期の米ソ戦略関係と国際安全保障政策-「デタント」と「対ソ強硬」の併存期における米国の戦略模索 1974-1977- 『研究論叢』第22号 |
| 令和5年3月 | 「レーガン政権のトライアッド領域での戦略戦力高度化に関する考察-対ソ核軍縮交渉の交渉力に連動する高度戦略優位構築の基幹的要素:NSDD12・35-69・73・91-178・252を中心として-」『研究論叢』第21号 |
| 令和4年3月 | 「レーガン政権期の対ソ核軍縮交渉における争点とリアリズム-NSDD256・NSDD271を中心として-」『研究論叢』第20号 |
| 令和3年4月 | 米国ハードライナーの大局的戦略形成要因としてのロングターム・スーパーパワー・リレーションに関する考察-超大国覇権・世界戦略遂行の「究極的力の後ろ盾」としてのストラテジック・オフェンシブ・アームスの長期的状況変化を中心に-」『研究論叢』第19号 |
| 令和2年8月 | 「大幅核削減・核廃絶を志向したレーガン政権の国際安全保障政策における対ソ・デモンストレーション・ファンクションとしてのリミテド・フォース・ユーズに関する考察-「高度戦略優位性実体の行使の可能性」を想起させた中東・カリブ海・中米での米国の行動を中心に-」『研究論叢』第18号 |
| 令和元年8月 | 「レーガン政権の対ソ核軍縮外交の特質としての「力(strength)・毅然性(dauntlessness)・対話(dialogue)」に関する考察-米国安全保障最優先課題「戦略核大幅削減・陸上中距離核全廃」を志向したレーガン外交の「1985年ドラマ」を中心に-」『研究論叢』第17号 |
| 平成30年11月 | 「レーガン政権期米国のSLCM・ASM135ASATと対ソ核軍縮外交-2つの非対称SA(ASA)と大幅核軍縮転換点の構築-」『地域連携研究』第5号〈通巻28号〉 |
| 平成30年8月 | 「レーガン政権の宇宙ベースブースト迎撃計画-冷戦終結のビックファクターとしてのSpace-Based Boost-Phase Intercept System(SBBI)に関する一考察-」『研究論叢』第16号 |
| 平成29年11月 | 「ジョンソン政権の国際政治戦略-米ソ戦略的パリティ化の大局と冷戦「局地戦」へのアメリカの対応-」『地域連携研究』第4号〈通巻27号〉 |
| 平成29年8月 | 「ケネディ政権の国際政治戦略-アメリカ国際政治戦略におけるリベラル・オプションの形成-」『研究論叢』第15号 |
| 平成28年11月 | 「アイゼンハワー政権の国際政治戦略-1950年代の冷戦と米国の国際政治戦略のマクロとミクロ-」『地域連携研究』第3号〈通巻26号〉 |
| 平成28年7月 | 「トルーマン政権の国際政治戦略-冷戦初期におけるアメリカの国際情勢認識の変化と戦略構築-」『研究論叢』第14号 |
| 平成27年11月 | 「冷戦におけるソ連の国際政治戦略の基幹原則-国際政治のメガトレンドはいかに形成されるか-」『地域連携研究』第2号〈通巻25号〉 |
| 平成27年7月 | 「国際政治の現実と国際政治学の理論-リベラリズムとリアリズムを中心として-」『研究論叢』第13号 |
| 平成26年11月 | 「国際政治における到達点と課題-王政間闘争・冷戦からグローバリゼーションまで-」『地域連携研究』創刊号〈通巻24号〉 |
| 平成26年7月 | 「冷戦と米国歴代政権の国際政治戦略:ルーズベルトからレーガンまで-冷戦の形成・展開・危機・終結とホワイトハウスの戦略の変化-」『研究論叢』第12号 |
| 平成25年11月 | 「アメリカの世界戦略展開の一構成要素としての日本の対米軍事技術供与-レーガン政権・ブッシュシニア政権下での日本の対米軍事技術供与始動への視点-」『地域研究』第13号〈通巻23号〉 |
| 平成25年7月 | 「国際政治経済におけるレーガン革命-グローバル資本主義への歴史的転換点創出としての1980年代アメリカ世界戦略の展開-」『研究論叢』第11号 |
| 平成24年11月 | 「レーガン政権の国際政治戦略と日米関係-1980年代アメリカ世界戦略における「日米同盟」の形成と展開-」『地域研究』第12号〈通巻22号〉 |
| 平成24年7月 | 「ワインバーガーの国際政治戦略-その構想と展開-レーガン政権のバックボーン・リーダーの戦略構想・戦略展開の視点からの1980年代アメリカ世界戦略の分析-」『研究論叢』第10号 |
| 平成23年11月 | 「レーガン政権の対中米外交に関する考察-対ソ連強硬路線を基調とした1980年代のアメリカ国際政治戦略体系の一構成要素としての対中米外交-」『地域研究』第11号〈通巻21号〉 |
| 平成23年7月 | 「レーガン政権の対ソ連外交とグローバライゼーションの地平-アメリカ国際政治戦略:「力による平和(Peace through Strength)」戦略の軌跡と成功要因-」『研究論叢』第9号 |
| 平成23年3月 | 「レーガン政権の対ソ連外交とアメリカ国際政治戦略のワンオプションの確立−1981年・1982年・1983年のアメリカの対ソ連外交を中心に−」『生涯学習研究年報』第5号〈通巻第14号〉 |
| 平成22年11月 | アメリカの科学技術系競争的資金制度の卓越性を実現するファクターズ−制度改善メカニズムFDPと研究大学におけるグラントオフィスを中心に−」『地域研究』第10号〈通巻20号〉 |
学会報告
| 平成20年10月 | 「日本の競争的研究資金制度の課題」研究・技術計画学会 第23回年次学術大会 |
|---|---|
| 平成11年5月 | 「経済政策の日米比較−独創的産業技術創造への政策対応」日本経済政策学会第56回大会 |
| 平成8年5月 | “The Theory of Industrial Policy” 日本経済政策学会第53回大会 |
| 平成4年11月 | 「発展途上諸国の開発戦略としての産業政策」国際開発学会第3回全国大会 |
略歴
| 令和5年9月 | 新潟大学大学院現代社会文化研究科博士後期課程共生社会研究専攻修了 博士(法学) |
|---|---|
| 平成26年10月 | 新潟大学大学院現代社会文化研究科博士後期課程共生社会研究専攻入学 |
| 平成19年4月 | 長岡大学経済経営学部教授(現在に至る) |
| 平成17年4月 | 長岡大学産業経営学部教授 |
| 平成14年4月 | 長岡大学産業経営学部助教授 |
| 平成11年4月 | 長岡短期大学経済学科助教授 |
| 平成6年4月 | 長岡短期大学経済学科専任講師 |
| 平成6年3月 | 法政大学大学院社会科学研究科経済学専攻博士課程単位取得満了 |
| 昭和63年4月 | 法政大学大学院社会科学研究科経済学専攻博士課程入学 |
| 昭和63年3月 | 法政大学大学院社会科学研究科経済学専攻修士課程修了(経済学修士) |
| 昭和61年3月 | 法政大学経済学部経済学科卒業 |
社会的活動
| 令和6年12月 | 第60回長岡社会保険委員大会において講演 |
|---|---|
| 令和5年1月 | 小国町商工会新春講演会講師 |
| 令和2年8月~ 令和3年3月 |
新潟県商工会連合会・商工会運営研究会委員 |
| 平成25年4月~ 平成26年3月 |
南魚沼市産業振興ビジョン策定委員会委員 |
| 平成21年12月 | 南魚沼市でのパネルディスカッション(「コンテンツ産業と連携したまちづくり」)にてコーディネーター |
| 平成21年3月 | 科学技術振興機構において講演 |
| 平成20年2月 | 山古志商工会において講演 |
| 平成20年1月 | 大和商工会女性部において講演 |
| 平成20年1月 | 長岡市公民館において講演 |
所属学会
研究・イノベーション学会、日本経済政策学会、国際開発学会、国際公共経済学会、日本国際政治学会、軍事史学会、政治経済史学会